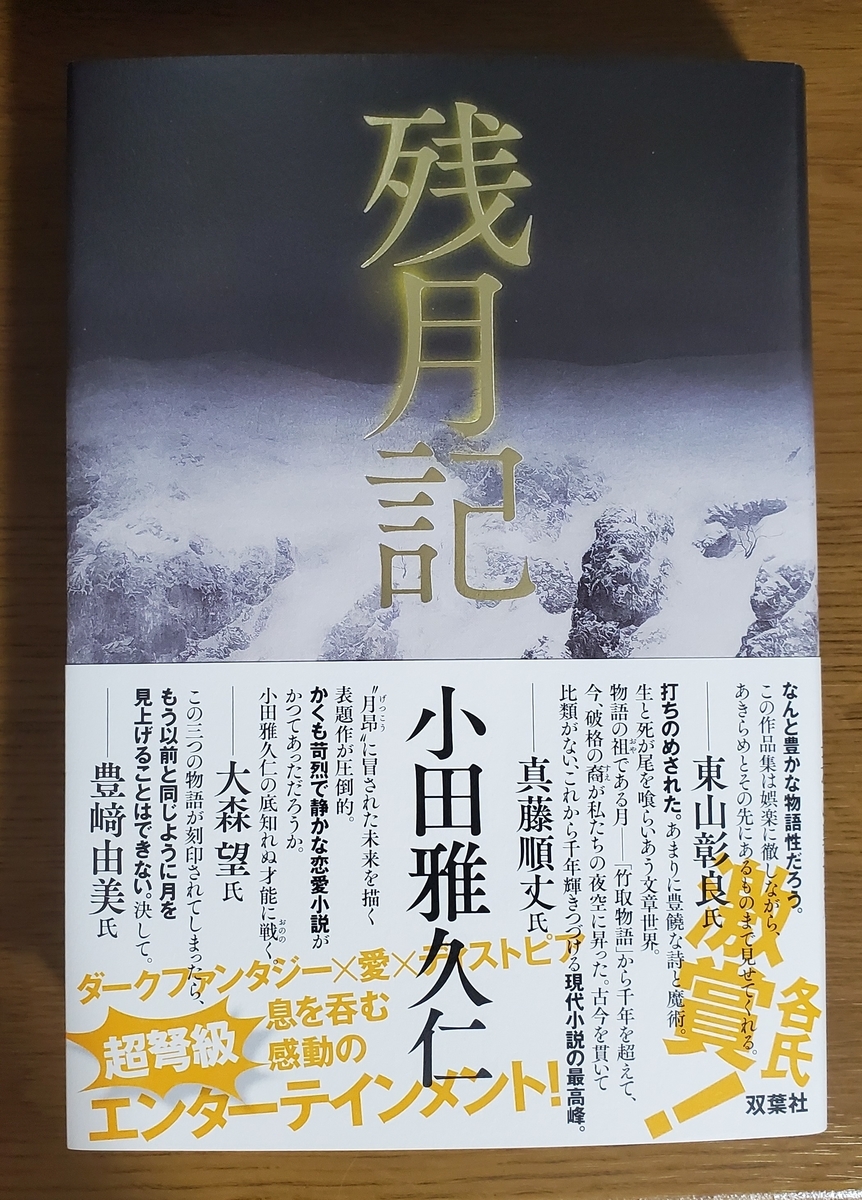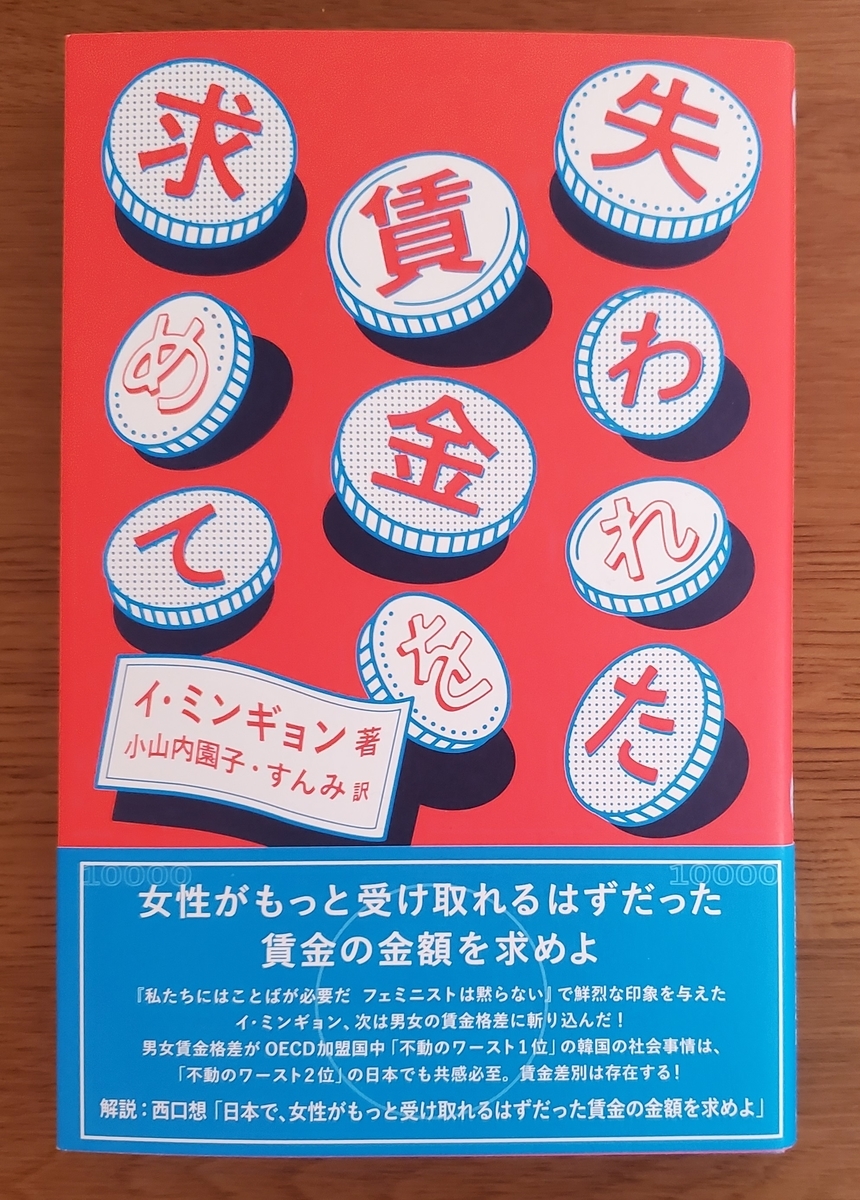2021年のM1-グランプリで、50歳と43歳のコンビ錦鯉が優勝したことが話題になった。M1はコンビ結成15年以内という参加条件があり、若手漫才師の登竜門的な位置づけになると思うのだが、そこで合わせて93歳という中年コンビが優勝したのは、芸人を目指す人にとっては希望となったかもしれない。
これはお笑いコンビ〈馬場リッチバルコニー〉が解散するまでの話。
大前粟生「おもろい以外いらんねん」は、その一文から始まる。物語は、“俺”(咲太)の視点で語られる。〈馬場リッチバルコニー〉は、俺の友人であるタッキーとユウキが結成したコンビだ。俺とタッキーとユウキは高校の友人で、タッキーとユウキは文化祭で漫才を披露した。本書の前半の半分くらいまでは、タッキーとユウキが〈馬場リッチバルコニー〉としてコンビを組み、文化祭で漫才を披露するに至るまでの3人の関係性と“俺”がふたりに対して抱く劣等感というか、ふたりと自分との間にある疎外感のようなものとの葛藤を描いている。
文化祭から10年。〈馬場リッチバルコニー〉はプロの芸人となり8年が過ぎた。お笑いファンの間での知名度はあるし単独ライブも満員になるが、まだ高い人気とまではいかない中堅若手コンビだった。新型コロナのパンデミックでお客さんを入れたライブや劇場公演ができなくなり、芸人たちはネットの配信番組などで糊口をしのいでいた。
〈馬場リッチバルコニー〉がプロになってからの物語は、プロの芸人が読んだら相当にリアリティがあるのだろうなと思う。実際、本書を読んで高く評価している芸人もいるようだ。私のような素人には、現実味はなかなか感じられるものではないが、コンビの関係性だったり、コロナ禍で芸人としての仕事が激減したり、お客さんの前でライブができないことで悩んだりすることは、共感とはいかないまでも理解できる気がする。
また、本書はあるお笑いコンビと彼らを見守る友人の葛藤だけを描いているわけではない。女性芸人の容姿いじりに対する違和感であったり、現代社会の有するさまざまな問題を受けて変化を求められていくお笑いの世界の苦悩もしっかりと盛り込まれている。タイトルの「おもろい以外いらんねん」には、「面白い以外の要素は不要」という意味とともに、「面白ければなんでもいいというわけではない」という意味も込められていると思う。そこが本書をただの芸人青春小説で終わらせていない要因なのではないだろうか。
錦鯉が優勝した2021年のM1には、6017組の漫才師がエントリーしていた。芸人として活動する人はさらにもっといるわけで、私たちのようなテレビでちょっとバラエティ番組をみているという程度の一般人にも知ってもらえるような芸人は、その大勢いる中でもほんの一握りでしかない。そのわずか一握りの存在になるために彼らは日々闘っている。生活のためにアルバイトをし、舞台に立ち続けている。夢と希望を胸にひたむきに頑張る姿はキラキラしてみえるが、その反面でなかなか日の目を見ないままに年齢を重ねていく姿には悲壮感も感じてしまう。そういう悲喜こもごも含めて芸人なのかもしれないが。
〈馬場リッチバルコニー〉も、いろいろと紆余曲折がありながら、ラストにはコンビとしてのある決断をする。それまでに少なからずも積み上げてきた実績を捨てて、新しく次の一歩を踏み出していくことは勇気のいることだろう。しかし、変化をおそれて現状にとどまっていては何も成長はできない。それは芸人の世界だけではなく、どのジャンルの世界でも共通していることだ。その共通点が胸にストンと落ちた時にこの小説の良さが実感できたように思う。