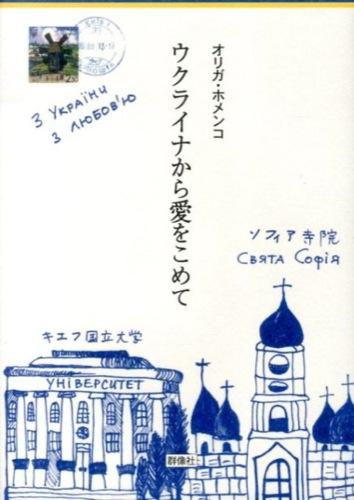これは、わたしたちの一夏の物語。
他の誰にも味わうことのできない、わたしたちの秘密。
乗代雄介「パパイヤ・ママイヤ」は、SNSで知り合ったふたりの少女が出会い過ごした短い夏の日々を描く青春ガール・ミーツ・ガール小説である。最近は青春小説を読む機会がなかったので、新鮮な気分で読んだ。
登場人物は、“パパイヤ”という17歳の少女と“ママイヤ”という17歳の少女。物語はママイヤの語り「わたし」で綴られる。SNSでつながりあったふたりは、わたし(ママイヤ)の「おそろいにしようよ」の提案でパパイヤとママイヤになった。ふたりの共通点は「親がむかつく」ということ。でもそれは他のフォロワーにもたくさんいる。ふたりを結びつけたのはお互いが同じ県の同じ市で5キロと離れていないところに住んでいるということだった。
こうしてふたりは、小櫃川河口の干潟ではじめて会うことになる。そして、ふたりにとって忘れられない夏の日を過ごすことになる。
背が高くてバレーボール部に所属しているパパイヤと、部活はやってなくてカメラや読書を少し楽しんでいるママイヤ。ママイヤは運動もあまり得意ではない。対称的なふたりがそれぞれに家庭的な悩みを抱えていて、それを補い合うかのように互いを必要としていくという関係性は、読んでいると不安な気分になったり、共感できたり、でもやはり17歳の少女とのギャップを感じたりする。
小櫃川河口干潟で会うことを繰り返す中で、ふたりはひとりの男の子が干潟にある木の墓場で絵を描いているところに遭遇する。男の子が黙々と描いた絵はとても上手だったが、なぜか空は一面黄色く塗られていた。思わず「なんで黄色?」と問いかける。男の子は「見たままを描いた」と答える。しばしのやりとりがあって男の子は絵を描き直すことにする。黄色い空を描いた絵は、パパイヤが大きなウイスキーのペットボトルに詰め込んで海に放り投げこんだ。
男の子と会った翌週、ふたりは小櫃川河口干潟でホームレスの男性と出会う。ホームレスは、“きいれえもん”を集めていると言う。“きいれえもん”、つまり黄色いもの。所ジョンと名乗るそのホームレスは、彼が集めた“きいれえもん”をふたりに見せてくれた。桐のコレクション箱を埋め尽くす黄色。
この物語に出てくるのは、パパイヤとママイヤそしてふたりが出会った男の子とホームレスの所ジョンの4人だけだ。そして、男の子と所ジョンは、最初の出会いの場面でしかほぼ登場しない。
空が一面黄色く塗られた絵ときいれえもんを集めているホームレス。パパイヤとママイヤは、所ジョンに男の子が描いた黄色い空の絵をあげようと思いつく。そのためには、パパイヤが海に投げ込んだ大きなペットボトルを探す必要がある。だからふたりは、夏休みを利用して、流されたペットボトルを探して小櫃川河口干潟から袖ケ浦海浜公園、さらには小櫃川河口干潟から富津公園までの海沿いを自転車やバスで走り回る。走り回りながら、ふたりはお互いの家庭のことや学校のことを話していく。短い夏の冒険(というにはちょっとこじんまりしているけれど)を通じて、ふたりは互いを知り、読者はふたりを知っていく。
とりたててドラマティックな展開があるわけでも、胸キュンなラブストーリーが待っているわけでもない。ふたりの少女の夏物語は、もしかするありきたりで物足りないものと感じられるかもしれない。だが、それこそがリアルなティーンエイジャーの青春なのではないか。この物語に描かれる少女たちの姿こそが、いまのリアルな若者たちを描き出しているのではないだろうか。
思えば、自分にもパパイヤやママイヤと同じように青春の時代があった。もうセピア色に褪せてはっきりと思い出すことも難しいくらい遠い過去の話。パパイヤやママイヤのようなSNSでのつながりも、それどころか携帯電話すらなかった時代の青春。だけど、気持ち的にはパパイヤやママイヤと同じバイタリティがあったと思う。
パパイヤとママイヤが出会う小櫃川河口干潟やふたりが冒険する内房の海沿いの場所は、いまも私が住んでいる地元の風景だ。袖ケ浦海浜公園(最近では地元出身のバンド氣志團が主催する「氣志團万博」の開催地として全国的に有名)の展望台も富津岬に建つ展望台も馴染みの場所だ。地元が舞台になった小説というだけで、私の「パパイヤ・ママイヤ」に対する好感度は爆上がりなのである。
ふたりが出会い語らった場所、男の子が黄色い空の絵を描いた場所、所ジョンがきいれえもんを集めていた場所、小櫃川河口干潟については、こちらのサイトが写真も豊富で詳しいので興味のある方は参照してみてほしい。ふたりが出会った木の墓場や所ジョンが住みついていた揚水ポンプ場跡の写真もある。
冒頭にも書いたが、こういう青春小説を読むのは久しぶりだった。読む前は「中年のオッサン読者に若い女の子の青春ストーリーなんて楽しめるのかな」と思っていた。地元が舞台になっているから興味をもって読んだけど、作品的に理解できるか楽しめるかは未知数だった。結果、理解できているかは(パパイヤ、ママイヤと私との世代ギャップもあることだし)未知数だけど、とても楽しく読むことができた。そして、遠い昔を思い出して懐かしくも感じた。ときにはこういう青春を思い出させてくれるような小説を読んで、気持ちだけでもあの頃の自分に戻れればいいなと思う。