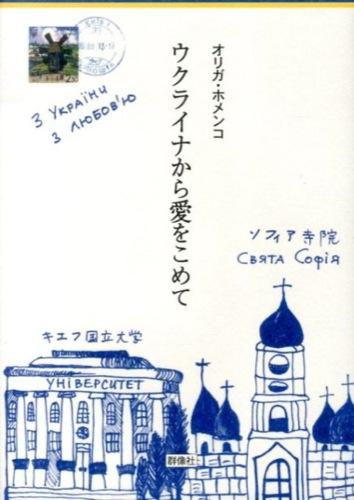何かを学ぶということは、長い人生において必ず自分の血となり肉となるということを人生も折り返し点を過ぎてゴール地点も視界に入ってくるようになった今強く感じている。
なぜそういう話から始めるかといえば、本書「夕暮れに夜明けの歌を 文学を探しにロシアに行く」が、奈倉有里さんがロシア語を学んでいく中で得た出会いであったり、ロシアという国で見聞した出来事が彼女の今を構成するとても大切な要素となっていると感じたからだ。
高校1年生のときに、「自分も英語以外の言語がやりたい」と考えた奈倉さん。“自分も”というのは、彼女のお母さんが“趣味として”ドイツ語を学び、さらにスペイン語も学んでいたからで(しかもいずれも独学である)言語を学ぶということに対するハードルが低かったのだろう。第1章「未知なる恍惚」で描かれる家庭内の描写(ドイツ語、スペイン語を学ぶお母さんが家中の家具や家電に単語を書き、ロシア語を学ぶ奈倉さんはそこにロシア語の単語を書く)や書店に行けば友人から「ロシア関連の本には見境がない」と言われるほどロシア語やロシア文学に関する本を手にとるほどにロシア語にのめり込んでいく描写が面白い。面白いと同時に、若い時にこんな風にすべてを捧げられるほどにのめり込めるものと出会えた奈倉さんを羨ましくも感じた。
こうして、「進路というものが自分にあるのならロシア語しかない」とまでになった奈倉さんは、2002年から2003年にかけての冬にロシアのペテルブルクに渡る。渡航の旅の途中で大雪によるトラブルに巻き込まれたりするが、親切なバイオリン弾きの紳士に助けられてなんとかペテルブルクに到着し、語学学校でロシア語を学ぶ。さらにモスクワにあるロシア国立ゴーリキー文学大学に合格し2008年に日本人としてはじめて同大学を卒業した。本書には、波乱のペテルブルク渡航時のエピソードから文学大学で学んだこと、ロシアで出会ったたくさんの人との思い出が記されている。それは、奈倉有里というロシア文学研究者、翻訳家の礎を築いた若き日のノスタルジックな思い出であり、真剣にロシア語、ロシア文学と向き合ってきた学びの記録である。
いくつか印象に残ったエピソードがある。第5章「お城の学校、言葉の魔法」には、ペテルブルクで通った語学学校で出会ったエレーナ先生のエピソードが書かれている。奈倉さんはエレーナ先生と出会ってロシア語で詩を読む楽しさを知る。ペテルブルクの大学で文学を学ぼうと考えていた奈倉さんにモスクワの文学大学を薦めてくれたのもエレーナ先生だ。そして、アレクサンドル・ブロークという詩人を教えてくれたのもエレーナ先生だ。奈倉さんが魅了されたブロークの詩の一部が本書内で引用されている。
僕は喜びに 向かっていた
道は夕闇の露を 赤く照らし
心のなか 息を呑み 歌っていた
遠い声が 夜明けの歌を[・・・]
心は燃え 声は歌った
夕暮れに 夜明けの音を響かせながら[・・・]
本書のタイトル「夕暮れに夜明けの歌を」は、おそらくこのブロークの詩の一節からつけられたのだろう。
アレクサンドル・ブロークの詩の魅力については、第17章「種明かしと新たな謎」でも記されている。「かの女」というブロークの代表的な作品を引用した上で、原語の“音”に魅了されたことを奈倉さんは書いている。詩に書かれていることの意味やブロークの伝記的事実はわからなくても、エレーナ先生の朗読を聞き、その音の響きに魅了された。そして、文学大学で出会ったアントーノフ先生の授業で「かの女」がもつ詩のリズムについて学んだことでさらに衝撃を受けることになる。本書ではもちろん日本語の訳詩となっているが、奈倉さんが魅了されたという原語の音の響きを機会があれば聞いてみたい。
本書ではエレーナ先生の他に奈倉さんが出会った人々についての思い出がたくさん記されている。ペテルブルクで出会ったユーリャという女子大学生。モスクワで出会ったインガというドイツからきた女子留学生。宿泊所で出会ったサーカス団の青年で道化師のサーシャとアクロバットのデニス。同じ学生寮で同居していたマーシャとは現在でも連絡を取り合う仲が続いている。
奈倉さんにとって一番の出会いは文学大学の文学研究入門の講座で出会ったアレクセイ・アントーコフ先生である。しょっちゅう酒を飲んでいることで学生の間でも有名人だったアントーコフ先生。でも、アントーコフ先生の最大の魅力はその授業にあった。彼が授業を始めると学生たちはその講義に魅了される。普段は酔っ払ってフラフラしている先生が、いざ授業となると人が変わったようにいきいきとして学生たちを講義の世界に集中させる。まるで作り話やマンガに登場するような人物だが、紛れもなく実在の先生だ。多くの人にとっては、こんな先生に出会うことは奇跡とも言えるくらい稀なことだろう。以後、大学を卒業するまで奈倉さんはアントーコフ先生に師事し、彼からたくさんのことを学んでいく。アントーコフ先生の授業での奈倉さんの存在感から創作科の学生からネタにされて、その創作があらぬ誤解に発展してしまったりもする。アントーコフ先生との数々のエピソードには、奈倉さんの先生に対するリスペクトの気持ちがギュッと詰まっていると感じる。そして、本書の最終章になる第30章「大切な内緒話」での卒業論文でのエピソードにつながっていくのである。
今、ロシアはウクライナへの軍事侵攻により世界的に非難されている。奈倉さんが学んでいた頃にもロシア国内とロシア周辺との状況はかなりひどいものだった。警察組織の腐敗やチェチェン問題などがあり、自爆テロ事件なども起きている。そして、その状況は今もなお変わらぬままに、クリミア併合や現在のウクライナ軍事侵攻へとつながっていく。そうした中にあって、奈倉さんは自分は無力であったと記している。そのうえで、無力でなかった唯一の時間があり、それは詩や文学を学ぶことで生まれた交流のときであったと記している。人は言葉を学ぶ権利があり、その言葉を使って世界中の人たちと対話する可能性がある。それが“分断”を生むのではなく“つながり”を生むにはどうしたらよいか。日本語以外のロシア語という言語を学び、ロシアで暮らして多くの出会いや多くの経験をしてきたからこそ、奈倉さんは言葉の大切さを感じているのだろう。
すでに多くの人が本書を絶賛している。今回、私自身も読んでいて、単純に面白いという他にいろいろなことを深く考えた。私は日本語以外の言語を知らないが、翻訳された文学作品やノンフィクションを読むことで世界を身近に感じることができる。この本は、言葉の持つ力について改めてじっくりと考えることを促してくれる本だと思う。考えること、そして理解することで相手との“つながり”を深めていく。いがみ合う世界ではなく分かり合う世界になることを祈るし、自分自身がそうなるように行動していきたいと思っている。